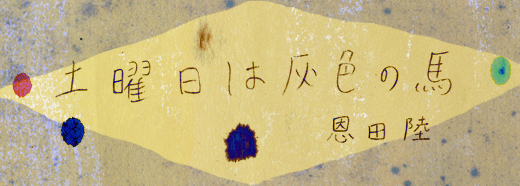
『フォース・カインド』(オラントゥンデ・オスサンミ監督)という映画を観た。
アラスカ州で実際に起きた事件を映像化したもの、という触れ込みである。
実話を基にした映画というのは珍しくないが、この映画の新味は、実際に監督が体験者をインタビューした映像や、事件の際に撮られていた映像をふんだんに再現映像に盛り込んでいるところだろう。
映画によると、アラスカ州のその地域は失踪事件の頻度が著しく高く、FBIの出動件数が突出して多い場所なんだそうである。その地に住む精神科医が、不眠症に悩む患者が多いことに気付き、カウンセリングで催眠術を掛けて原因を探り出そうと話を聞いてみたところ、誰もが似たような体験をしていることに気付く──というものだ。
実際に何が起きたのか、精神科医が導き出した仮説が正しいのかどうかは監督も明言せず、観た者に判断を委ねる、という結論になっている。
話の真否や映画の出来はともかく、私はこの映画を新手のホラーとして興味深く観た。
以前から、バリバリのホラーサスペンスを一本書いてみたいなと思っていたのだが、これだけホラー映画やホラー小説、実録怪談ものが隆盛を極めている現代、果してどういうアプローチがよいのか、どういうものが怖いのか、ずっと考えあぐねていたからだ。
しばしば、「怖い本を教えてくれ」という質問や、「これまでにいちばん怖かった本は」というアンケートを受けたりする。
その都度、「怖いってなんだろう」と悩んでしまう。「怖さ」というのは人種や世代を超えて普遍的な感情であるのと同時に、極めて個人的なものでもあるからだ。
虫が怖い、不潔なものが怖い、猛獣が怖い、病気が怖い、ストーカーが怖い、失業が怖い、災害が怖い。こういった圧倒的に物理的で現実的な「目に見える」恐怖に、我々は日々脅かされているし、実際こういうもののほうが待ったなしで解決を迫られることも含め、暴力的に怖い。
しかし、そのいっぽうで「目に見えない」恐怖、「存在しないとされている」恐怖というものは確実に存在するし、私が興味を覚え、描いてみたいというのはもちろんこちらのほうなのだ。
『フォース・カインド』は「存在しないとされている」恐怖を「見せずに見せる」アプローチに可能性を感じた。インタビュー映像、カウンセリング映像、警察の監視映像という一次資料を使って「間接的」に見せるテクニックは参考になった。
それにしても、写真やビデオ映像など、「撮られた」ビジュアルというのはどうしてああも気味が悪いのだろう。実物を写しながらも「もしかして、細工をしたのかもしれない」とふと脳裡をよぎる疑惑。フレームの外にフレーム内とは全く異なるものがあるのではないかという欺瞞の予感。いわば虚構の入り込む余地があるが故に逆に本物かもしれない、という、いかがわしさすれすれのグレイゾーンがあるところが怖いのではないか。
先日、人とゴーストストーリーについて話していた時、スティーヴン・キング、特に『シャイニング』を境として、いわゆるゴーストストーリーは途絶えたのではないかという説が出た。
要は、八十年代以降の「モダン・ホラー」は、面白すぎるのである。サイコホラーの登場もあってジャンルは細分化し、テクニックは洗練され、メガヒットも出て人材も豊富になった結果、私にとってのモダン・ホラーは完全にエンターテインメントとなり、「こわい」と感じたことが全然ない。
本来、ゴーストストーリーは地味でそっけなく、隙だらけでカサカサしているのである。
それは、いわば昔話や思い出話を聞かされる感覚だ。普通の顔をしていて、知っているつもりで、聞き飽きた心地すらする。日常、ふと宴会が終わって数人だけ残り、汚れた皿や空っぽの酒瓶を前に煙草を吸いながら、「今にして思えば」とか「誰かに聞いた話なんだけど」という前置きになんとなく始まる話。オチも解説もないけれど、一瞬、ザラザラとした手が肩を撫でていったような感覚。それが私の考える「こわい」、私の求める「こわい」なのである。
何より、私は「今にして思えば」や「誰かに聞いた話なんだけど」というフレーズが怖いのである。特に最近気になるのは「今にして思えば」だ。
過去のある時点を振り返り、あれは何だったんだろうと考える。当時は目にしていてもなんとも思わなかった。あるいは、渦中にいて状況が理解できなかった。しかし、今ならば視点や視座が変わり、何が起きていたのか分かる。そして、改めてゾッとしたり、冷や汗を掻いたり、笑いが止まらなくなったりする。
そう、これが「こわい」なのだ。「こわく」なるのは「気付き」があった時であり、何かを発見した時なのである。また、「気付いた」時に、「気付く」前との落差が大きければ大きいほど、「こわい」も大きくなる。
これは以前にも書いたことがあるのだが、そんな「気付き」の「こわい」体験といったとき、思い浮かぶものが二つほどある。
ひとつは朝の通勤電車。いつものように混んでいたが、一人、素敵な女の人が前に座っていた。五十歳を越えているくらいだったが、加齢がマイナスになっていない美しさで、身に付けているものもとてもお洒落。チラチラ眺めて、こんなふうに歳を取りたいなあと思っていたところ、終点の駅に着いた。ぞろぞろと通勤客が下りていき、彼女はスッと立ち上がった。その時、彼女が膝の上に大きな金髪の女の子の人形を抱えていたことに気付いたのだ。
目にした瞬間、一瞬頭の中が真っ白になった。なぜ剥き出しのまま人形を?
彼女は平然とした表情で人形を無造作に小脇に抱え、カツカツとハイヒールの足音も高く改札口に向かって歩いていった。その後ろ姿を見ながら、初めてゾーッとしたのだ。異様さを感じたのは私だけではなかったらしく、彼女とすれちがうビジネスマンたちが、皆怪訝そうな顔で振り返っていた。
もうひとつは、やはりOL時代、友達と飲んで、飲みなおそうとアパートに夜中帰ってきた時のこと。私が当時住んでいたアパートは一階に三世帯、二階に三世帯というこぢんまりしたアパートで、住んでいたのは皆女性だった。私は一階のいちばん奥に住んでいたのだけれど、友人とわいわい喋って通路に入ったところ、一階の真ん中の部屋の前に、一人の女の子が立っていたのである。
髪の長い女の子で、二十代の若い子だった。私と友人は彼女の後ろを通って自分の部屋に入ったのだが、翌日になって、いったいあの子はなんだったのだろうと友人と話しているうちにだんだん怖くなってきた。なにしろ、夜中の一時過ぎ、しかも雨が降っていて寒い夜だった。なのに、彼女はドアの前で直立不動、ただじっと立っていたのだ。私たちが通り過ぎる時も微動だにせず、ドアに顔をくっつけんばかりにしていたので顔も見えなかった。
思い出してもこのふたつは怖い。もしかしたら他愛もない話だったのかもしれないが、いろいろに解釈できるところがどうにも「こわい」のである。
私が怖いと思う本も、シンプルなのに漠然とした怖さを持っているものだ。
怖い小説、といって今でもいちばんに挙げるのは、アガサ・クリスティの『終りなき夜に生れつく』である。
この小説、クリスティ自身とても愛着を持っていたらしいが、なんだか分かるような気がする。全編を覆う不吉で哀切な雰囲気、澱みなくするすると語られる物語が恐るべき真相へと集約されていくさまが美しいのだ。
しかし、とにかく怖い。登場人物の会話がどこをとっても不吉。
中でも最も怖かった場面は、田舎に越してきた主人公が環境に適応し、「とてもうまくいっている」と近所の人間に話すと、彼は眉をひそめて、「それは気をつけなければいけない。それがフェイというやつで、何かの災厄の前にやってくるものだから、ごきげんな気持ちを抑えたほうがいい」と言うところである。ここだけ抜き出しても怖さは伝わらないかもしれないが、「フェイ」という言葉の響きや上機嫌に水を差すような不穏な忠告との落差にゾッとさせられる。
あるいは、フィリップ・K・ディックの『死の迷宮』。遭難状態の宇宙船の中で、乗員が殺されていく。クローズド・サークルの中で、皆が精神的に破綻していくあいだにも何も変わりないような日常会話が延々と交わされる場面。
日本の小説ならば、短編が圧倒的に怖い。川端康成、谷崎潤一郎、佐藤春夫、稲垣足穂。近代の小説は、とにかく恐怖に満ちている。内田百けんならば、私は「サラサーテの盤」よりも「東京日記」が怖い。いつも通りの何気ない顔でどう考えても異常な状況を語るその「普通の何気なさ」が恐ろしいのだ。
しかし、最も怖いと思う本は、なんといっても聖書である。「怖い本」のアンケートを受けるたびにそう書いてきた。
私は子供の頃はプロテスタント系の幼稚園に通い、いっとき教会の日曜礼拝にも通っていたのだが、毎回語られる聖書の逸話に漠然とした恐怖感を覚えていた。「葡萄酒は私の血であり、パンは肉である」というのが恐ろしく、十二月になると紙で造った葡萄の木に自分の名前を書いた葉っぱの形をした紙を貼るのも怖かった。
大きくなって、高校時代に古典としてひととおり旧約聖書から新約聖書までを読んでみたが、そのあまりの不条理さに愕然とした。そこに描かれている神の行動はどうにも支離滅裂で、実に気まぐれに(としか思えない)人間たちに凄まじい災厄を与えるのである。その理由も説明されず、説明されたとしても全く納得できないような勝手な理屈なのだ。このようなテキストが成立した過程やテキストを支持してきた人々の情念を思うだに、ひしひしと恐ろしい。
かくも「こわい」は漠然としていて、説明不能で、ぼんやりとして輪郭がない。姿を現さない。形を見せない。見せずに観客自身にそれぞれの「恐ろしいもの」を想像させることがいちばんの「こわい」ものなのだ。
やはり怖いということでは横綱級のシャーリイ・ジャクスンの小説『山荘綺談』は二度映画化されているが、CGを駆使した二度目のものよりも、モノクロの最初の映画化のほうが断然怖かった。ふわりと揺れる白いカーテン。階段の上から射し込むかすかな光。そういったおぼろげな気配のほうが、観る者の心の底で共有している原始的な恐怖を駆り立てる。
『フォース・カインド』もいちばん気味が悪かったのが、カウンセリングを受ける患者が催眠術を掛けると、皆「窓のところに白いフクロウが来るんだよ」と苦しそうに告白するところである。
白いフクロウ。
そんな、恐怖の形を小説にしたいという欲求は、かなり人間の根源的なところに根ざしているような気がする。
「こわい」小説を書くにはどうすればいいのか。今、何が「こわい」のか。恐らく、この先歳を重ねるごとに、その時その時で「こわさ」は異なってくるのだろう。これは物書きとしての私にとって、永遠の課題である。
(2010.1.26)
