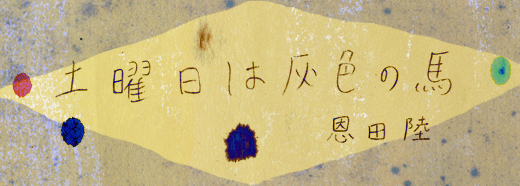
(1)
映画『ドリームガールズ』のDVDを繰り返し観ている。
私は密かにミュージカル好きで、『ドリームガールズ』も公開中に三回観ているが、最近DVD版が発売されたので、気に入ったナンバーの場面をしつこく観ている。ボーナス版として入っているメイキング映像の出来が素晴らしく、キャストのオーディションをはじめ、照明デザイナーやプロダクト・デザイナーらスタッフの仕事も丹念に追っていて見応えがある。
『ドリームガールズ』は元々ブロードウエイミュージカルとして舞台から出発した、女性三人の黒人ヴォーカルグループのサクセスストーリーである。図抜けた歌唱力でリードヴォーカルを取っていたエフィは、マネージャーの意向でリードを降ろされ、容姿の優れたディーナがリードに収まる。このディーナ役を映画ではビヨンセ、エフィ役をジェニファー・ハドソンが演じている(舞台ではジェニファー・ホリデイが演じた)。
ビヨンセは人気グループ「デスティニーズ・チャイルド」のリードヴォーカル。父親は音楽界の大プロデューサーで大金持ちだが、子供の頃からプロ志向が強く、小学生時代から自分でグループを作って地道に活動を続けてきて、二十歳そこそこの若さで成功した。その独立心とプロ根性には見上げたものがある。彼女はディーナ役を熱望し、モデルとなったヴォーカルグループ、シュープリームスの当時の映像を徹底的にリサーチしてオーディションに臨み、振付やファッションも自分で考えてきたという。
いっぽうのエフィ役、ジェニファー・ハドソンは新人。TVのオーディション番組「アメリカン・アイドル」で最終まで残ったズバ抜けた歌唱力の持ち主だが、審査員にはルックスなどで「君にはアイドルは無理」と酷評されて優勝を逃した経緯がある。
映画版『ドリームガールズ』は、登場人物と出演者の人生が重なることでも話題になり、ジェニファー・ハドソンは初出演のこの映画でアカデミー賞の助演女優賞を獲得した。
だがしかし、もちろん図抜けた歌唱力を必要とするエフィ役を捜すのが大変だったのはよく分かるが(メイキング・フィルムでは、エフィ役探しのオーディションにかなりの時間が割かれている)、それでもなお、映画『ドリームガールズ』が成り立ったのは、ディーナ役にビヨンセを得たことが大きいと思うのである。
第一、今のこの時代、「容姿はイマイチだけど歌唱力はすごいのよ」というタイプが既にもうピンと来ない。一人一芸の時代はとっくに終わっていて、今は総合力の時代なのだ。現代の日本の女の子で、この映画を観てエフィに感情移入する人は少ないと思う。なにしろ、エフィは「あたしのほうが歌がうまいのに、ディーナはあたしの男と寝てリードを盗った」と思い込み、不貞腐れて仕事をすっぽかしてしまう女なのである。美人でプロ意識が強く、フェアな態度のディーナのほうが、現代の女子にはよほど納得できるし、憧れる。実際、ビヨンセは自分のグループでも「遅刻したり、練習にやる気が感じられなかったり、プロとしての向上心のない人には辞めてもらった」そうなので、イメージにぴったり重なっていたし、その美女っぷりたるや、最近大味な「美人」女優ばかりのハリウッドで久々に「美女を見た」という感じでうっとりした。この完璧なディーナ役あってこそのエフィ役なのである。
(2)
とまあ、ビヨンセよりジェニファー・ハドソンの評価が高いのに疑問を感じていたためつい熱が入ってしまったが、最近また良質のミュージカル映画がぽつぽつ現れるようになって、とても嬉しい。
かといって、そんなに昔からミュージカルが好きだったわけではない。大学に入るまでに観たことのあるミュージカル映画はせいぜい『ウエスト・サイド物語』や『雨に唄えば』程度だったし、むしろ子供の頃は誰でも抱く疑問──「なぜ話の途中で唐突に歌い出したり踊り出したりするのか?」──が強く、ヒッチコックの映画やスパイスリラーなどが好きだったので、ミュージカルは苦手だった。
それがなぜ、大学に入ってミュージカルが好きになったかといえば、大学でビッグバンドに入り、ジャズを聴くようになったからだと思う。
バンドで演奏するスタンダード・ナンバーと呼ばれる曲は、映画やミュージカルで使われた曲が多いからだ。有名なところでは、「アズ・タイム・ゴーズ・バイ」が「サム、その曲は弾くな」とハンフリー・ボガートが呟く映画『カサブランカ』で使われた曲。「そうだ 京都、行こう」というキャッチコピーのJR東海のCMで、アレンジを変えながらもずっと流されている「マイ・フェイバリット・シングス」は映画『メリー・ポピンズ』の中の一曲。今はもうないが、かつて「日曜洋画劇場」という、淀川長治が解説者を務めた映画番組のテーマソング「ソー・イン・ラブ」は、元々は『キス・ミー・ケイト』というシェイクスピアの『じゃじゃ馬馴らし』を下敷きにしたミュージカルの中の曲である。
知っている曲が増えるにつれ、出典の映画も少しずつ観るようになっていった。東京に来て、名画座に行けるようになったことも大きい。
そして、ジャズを聴いていると、タップダンスを観るのが各段に面白くなるのである。タップのソロはジャズのドラムソロを聴いているのに近いところがあるので、即興のステップを観るのが楽しくなり、より凄いステップを観たくてミュージカルを観る、という循環が出来上がり、ミュージカルが好きになったというのが自分に対する分析である。
ミュージカル映画におけるタップダンサーといえば、フレッド・アステアとエレノア・パウエルだろう。私はアステアと名コンビを組んだジンジャー・ロジャースにはあまりピンと来ないのだが、エレノア・パウエルのステップにはいつも興奮させられる。アステアとパウエルは『踊るニュウヨーク』ぐらいでしか組んでいないが、ここで踊るパウエルはすごい。
アメリカのSF作家にコニー・ウィリスという人がいて、この人はハリソン・フォードの熱狂的なファンとして知られているが、熱心なミュージカル映画ファンとしても知られていて、バーチャル技術を進歩させて映画の中でフレッド・アステアと踊るのが夢という女の子と、映画監督を目指す男の子との恋を描いた、ミュージカル映画への愛満載の『リメイク』という小説を書いている。
その中で、ウィリスはヒロインに「フレッド・アステアは好きだけど、ジーン・ケリーはあんまり」と言わせている。いわく、ジーン・ケリーは「いかに自分が凄く難しいことをやっているか」を誇示するように踊るが、アステアは「恐ろしく難しいステップなのに、今ちょっと思いついたのでやってみた」というように踊るから好き、というのである。この意見はウィリスの意見だと思うが、納得させられるところがある。
私はジーン・ケリーも好きだが、彼の「力の入った」ダンスには、観ているほうもつい力が入ってしまう。けれど、アステアの軽やかなダンスは、観ているうちにふーっとこっちの身体まで浮かび上がりそうな気がしてくる。
アステアが完璧主義者なのはつとに有名だが、計算され尽くし、周到な練習をした上で生じるあの「軽み」を獲得したダンサーは彼以外に見当たらない。決して体格的に恵まれているわけでなく、若い頃から老け顔なのに、燕尾服にシルクハット、手にはステッキといういでたちがぴたりと嵌まり、踊っているどの瞬間のポーズも決まっていて、エレガントな空気感を漂わせる。スローモーションやアニメ合成、群舞が普通のテンポで踊っている映像に倍テンポで踊る自分の映像を重ねるなど、いろいろ実験的なことも試みているが、彼が踊っていると、コマ落としのようにそれぞれのポーズが止まって見えるのは、彼の持つタイム感が正確で、一瞬たりとも意識されていないポーズがないからだろう。
(3)
アステアの映画で好きなのは、エレノア・パウエルと組んだ『踊るニュウヨーク』はもちろんだが、ジュディ・ガーランドと組んだ『イースター・パレード』と、シド・チャリシーと組んだ『バンド・ワゴン』である。どちらもショー・ビジネスものだ。
ジュディ・ガーランドという人は、どこかで小林信彦も書いていたが、時折目に狂気の光を宿すというか、イッちゃってる目をする人で、天才少女歌手と言われてきて、出世作となった『オズの魔法使い』でも既にその萌芽がある。この映画の有名なナンバー「オーバー・ザ・レインボウ」は、アメリカ人にとってジュディ・ガーランドをはじめどことなく不幸な因縁を感じさせるナンバーだというドキュメンタリーを見たことがあるが、やはりイギリスの舞台を映画化した『リトル・ヴォイス』のクライマックスシーンでも使われていた彼女の歌「カム・レイン・オア・カム・シャイン」はなんとも身の毛のよだつような迫力のある演奏で、聞く度にぞっとするほどである。それでも、『イースター・パレード』のガーランドは本来のファニーフェイス系のキャラクターがぴったり嵌まっていて、アステアと組んで出た舞台の場面もご機嫌。元々ジーン・ケリーが演じるはずで、もう引退したと思われていたアステアが素晴らしいダンスを披露して復活したというおまけつきの映画だ。
『バンド・ワゴン』でも、なぜかアステアは落ち目のスターという役どころで出てくる。友人の脚本家夫婦と、新たな舞台を作って巻き返そうと、バレエダンサーのシド・チャリシーと組む話。
シド・チャリシー様(チャリースと読むという説もあるが、子供の頃からチャリシーで覚えているのでこれで通す)は、ミュージカル映画女優でいちばん好きな女優だ。ノーブルな美女でスタイル抜群、踊りも迫力満点。エルンスト・ルビッチの『ニノチカ』を下敷きにした、同じくアステアと組んだ『絹の靴下』もよかったが、やはりこの『バンド・ワゴン』のチャリシー様が一等素敵である。この映画のせいで黒髪ショートの美女というのに弱くなり、当然映画版『シカゴ』のキャサリン・ゼタ・ジョーンズ様にもうっとり。
チャリシー様は『ザッツ・エンタテインメント』でも案内役として登場していたが、歳を取ってもピンと背筋が伸びてとてもスタイルがよく、ノーブルな美しさは変わっていなかった。そして、なぜかDVD版の『アニーよ銃をとれ』もチャリシー様が紹介していて(権利の関係か、ずっと待っていたが『アニーよ銃をとれ』はついにビデオ版が出なかった)得した気分になったものである。『アニーよ銃をとれ』は元が舞台で、映画化にあたり当初ジュディ・ガーランドが主演するはずだったが、健康上の理由で降板してベティ・ハットンが演じ、当たり役となった。ハットンは実に溌剌としたアメリカ美人で、表情豊かで豪快な感じがぴったりだった。ガーランドではこうはいかなかっただろう。
さて、ミュージカル映画に似て非なるものに音楽映画というものがある。歌って踊り、ショービジネスを描いていても、ミュージカル映画ではないものもあるのだ。
ロイ・シャイダーがボブ・フォッシーをモデルにして振付兼演出家を演じた『オール・ザット・ジャズ』は全編歌と踊りに溢れているが、ミュージカルではない。映画版の『コーラスライン』も怪しいと思う。グレゴリー・ハインズとサミー・デイヴィス・Jrのタップダンスが素晴らしい『タップ』も違う。最近では、バイ・セクシュアルだったコール・ポーターの生涯を描いた『五線譜のラブレター』なんかも。
これらは、人生の直喩あるいは暗喩として歌と踊りが使われている。
いけません。邪道である。そんなのは、ミュージカル映画ではない。
ミュージカル映画は、歌と踊りの素晴らしさを強調するために、いわば音楽を引き立てるスパイスとして、音楽に深みを与えるために人間の人生が使われているのである。
これは非常に大きな違いだ。『ドリームガールズ』は、なるほど主要人物六人の人生の紆余曲折を描いた映画ではあるが、決して歌と踊りは彼らの人生に隷属してはいない。だから素敵なミュージカル映画なのだ。
(2007.9.11)
