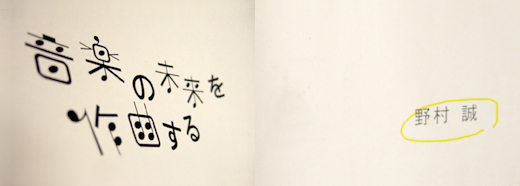
1 採譜からセッションへ
音楽の未来を作曲する上で、やはり大きなテーマとして「動物と音楽を作曲する」ことがある。動物と音楽を演奏することは可能だけど、作曲することは可能なのだろうか? では、そもそも作曲するとは、どういうことなのだろう? 動物との音楽の場は、そうした問いを見直す場になっている。
そもそも、動物を主題にした作曲は、作曲を始めた当初からあった。ぼくが8歳で初めて作曲したピアノ曲は「キツツキとアホードリ」、11歳で作曲したピアノ曲は「タヌキとキツネ」で、どちらも動物を題材にしている。もちろん、これらの作品は当時のぼくが動物に抱いていたイメージを音楽にしたのであり、作曲するにあたって動物たちと実際に関わりを持ったわけではない。しかし、自分の原点となる作品が、動物をタイトルにしていたことを確認しておきたい。
動物を愛する音楽家と言えば、数多くいるだろうが、20世紀を代表するフランスの作曲家オリヴィエ・メシアン(1908ー1992)の鳥の偏愛ぶりは有名だ。メシアンは鳥類学者について学んだりもしていて、特に1950年代以降は、「鳥のカタログ」、「鳥たちの目覚め」、「異国の鳥たち」など鳥をテーマにした作品を数多く書いている。頻繁に森に入り、鳥の鳴き声を可能な限り忠実に、五線譜に採譜していたらしい。メシアンの音楽は、鳥から多くを学んでいるのだ。
中学生の頃、ぼくは純粋にメシアンに影響を受け、メシアンの真似をした。つまり、森の中で鳥たちの鳴き声を聴いて、それを楽譜に書こうとしてみたのだ。ところが、鳴き声を楽譜に書こうと始めてみると、なんだか変だと思った。鳥はそもそも人間の12音階でも歌っていないし、楽譜に適したリズムなどでは歌っていない。だから、楽譜に書くとすると、何か近似値的に人間の音階に翻訳する作業が必要になる。ところが、翻訳していると、次の鳥がまた鳴き始める。一々、翻訳しているのが、だんだんバカバカしくなってくる。
そこで、まずは鳥の鳴き声を、できるだけ忠実に声で真似してみようと思った。こうやって真似するのは楽しいのだが、それは乳児が大人の言葉を真似しながら言葉を覚え始める過程に似ている。または、外国人が新しい言語を覚え始めているプロセスにも近いと思った。
鳥が鳴いている。何かを喋っている。それに一言も答えずに、ただただ真似したり楽譜を書いているのは失礼だ。それに、誠心誠意で答えるべきではないか。ぼくは鳥と会話をしたい、鳥と共演したいと思った。
逆に言うと、どうしてメシアンは鳥と会話をしなかったのだろう? 鳥と共演するための音楽を作曲してもよかったはずだ。鳥とメシアンの関係は、常に鳥が演奏家で、メシアンが観客という役割で固定されている。しかし、メシアンが演奏家で鳥が観客になって役割が反転することだって、あり得たはずではないか。
メシアンは鳥の音楽を模倣しアレンジを加えて、人間の世界で人間のために作品を発表した。鳥の世界で作品を発表することはない。でも、ぼくは思う。人間が鳥の音楽から影響を受けるんだったら、鳥の音楽だって人間に影響されて変わっていったっていいではないか。それがコミュニケーションであり、異文化交流だ。だから、ぼくは採譜する(模倣する)を超えて、鳥とセッションをしたい、コミュニケーションを試みたいと思った。ぼくは「動物との音楽」をしたいと思った。
2 参考事例「動物と音楽」
「動物と音楽」というアイディアは、到るところで見受けられる非常にポピュラーな発想だ。例えば、グリム童話に「ブレーメンの音楽隊」という物語がある。年老いたロバ、イヌ、ネコ、ニワトリがブレーメンに行って音楽隊に入ろうとするが、その途中で泥棒たちの家を見つける。動物たちは泥棒を追い出し、その家で音楽を奏でながら幸せに暮らした、という物語だ。実際に動物たちはどんな音楽を奏でたのか? 音楽についての具体的な記述がないので、それは空想するしかない。
ロシア(旧ソ連)にセルゲイ・クリョーヒンという前衛ジャズピアニストがいた。1989年、「新しい地平」と題されたコンサートを作曲家の高橋悠治が企画し、クリョーヒンが初来日するのをぼくは見に行った。ロシア人の友人にこのコンサートの報告をすると、クリョーヒンのコンサートはモスクワではもっとスゴイんだ、犬や猫だって出てくるんだ、と言う。犬や猫が出て来るコンサートと聞き、ぼくは単純に見てみたい、聞いてみたいと思った。一体、クリョーヒンと動物たちはどんな音楽をするのだろう? 動物がただ出てくるのか? いやいや、動物の鳴き声と即興でセッションするのか、それとも動物が楽器を演奏するのだろうか?
ぼくの頭の中で、想像はどんどん膨れ上がっていった。ちなみに、クリョーヒンは1996年に開かれたミュージック・マージュ・フェスティバルに来日する予定だった。ぼくは、そのフェスティバルに参加していたので、動物のことは直接質問してみようと楽しみにしていたのだが、フェスティバル直前に、クリョーヒンは帰らぬ人となり、話は聞けずに終わってしまった。
90年代初頭に、同世代のユニークな美術家と次々に知り合った。鳴海暢平は、犬の視点から人間社会を見るということを美術作品にしていた。では、犬の耳からは、この世界はどう聞こえているのだろうか? そんなことを考えさせられた。
また、島袋道浩は、1992年に京都の岩田山で「猿のための展覧会」をした。この話に影響を受けて、「猿のための音楽会」をやってみたいな、と考えたが、人間が演奏、猿が観客では、つまらないな、と直感した。ぼくがやりたいのは、「猿のための音楽(Music for monkeys)」ではなく、「猿との音楽(Music with monkeys)」だ。猿は観客になってもいいけれど、できれば演奏者として共演もしてもらいたい。
ゾウが楽器を演奏しているユニークなCDがある。エリオット・シャープなど現代作品を演奏しているソルジャー弦楽四重奏団でも知られるデイヴ・ソルジャーが、リチャード・ライアーと発表したCD「Thai Elephant Orchestra」だ。タイのゾウがガムラン的な打楽器を演奏していて、どうやらゾウが演奏するためにわざわざ楽器を作ったらしい。ゾウたちは長い鼻を器用に用いて、楽器を演奏して、録音。どのような方法で録音しミックスされたのか、詳細は不明なのだが、ゾウの演奏するリズム感の適度なバラバラ具合が、非常に心地よい。デイヴ・ソルジャーはゾウのために楽器を作ったが、自身はゾウと共演してみようとは思わなかったのだろうか? ぼくは、ゾウと共演して音楽を創作することを夢見る。
また、動物ではないが、作曲家の神津善行が「植物と話がしたいー自然と音の不思議な世界」(講談社)という本を書いていて、そのことからも間接的には大きく影響を受けた。
3 「動物との音楽」への前奏曲
初めて動物にコンサートに出演してもらったのは、1993年だ。即興ギタリストのデレック・ベイリーが来日したので、山梨は白州でのコンサートを見に行った。野外ステージでの集団即興演奏だったのだが、何か予定調和な気がして、今ひとつ納得できずにぶらっと席を立った。すると、猫じゃらしを使って猫と遊んでいる子どもと出会った。ぼくは、その子どもと猫のやりとりを見て、こっちの方がよっぽど即興で予測不能だなぁと感じた。ぼくもこの猫と即興をしてみたいと思った。そんなぼくの気持ちを察したのか、少年は猫じゃらしをぼくに手渡してきた。ぼくは猫と戯れながら、ベイリーのいるステージにどんどん近づいて行った。そして、ステージの前を行ったり来たりした。
この体験を面白く思ったぼくは、同じことを、京都のドイツ文化センターでの演奏会(フルクサスを特集していた)でやってみようと思った。各自が指示に従いながら即興で楽器を演奏するピースに、猫と出演することにした。白州での体験がイメージでき、それよりも一歩踏み込んだことができれば、と考えた。しかし、よく考えれば、猫の了解もとれていないし、自分勝手に猫を巻き添えにしていたのだ。ステージ上でピアニスト大井浩明らが演奏する音に猫は怯え、会場からロビーへと一目散に逃げ出した。ぼくの目論見「猫との音楽会」は失敗に終わり、もっと猫とコンセンサスを持って臨まなければ、意味がないと反省した。
1994年、大阪の天王寺動物園の近くの路上で、美術家の島袋道浩、杉岡正章鶴、ダンサーの山下残、砂山典子らと路上演奏をしていた時のこと。ぼくらは人間に聞かせるつもりで、路上演奏をしていた。ところが、人間は無視して通り過ぎて行くのに、突然、遥か彼方にいる動物園の動物たちが大声で鳴き始めたのだ。姿は見えないけれど、音は届く。動物たちは明らかに音楽に反応している。それは喜んでいるのか、怒っているのか、さっぱり分からないけれど。動物たちも音楽に反応して何かを言ってくるならば、ぼくもそれに反応して即興でやりとりをすればいい。動物との音楽の共演への確かな手応えを得た。
しかし、それから具体的なチャンスはなく、「動物との音楽」が具体化したのは2003年になる。イギリスのバーミンガムにある美術館Ikon GalleryからIkon Performance Weekendに出演の依頼が来たので、ペットを連れて来てもいい音楽会「Music with Pets」を提案した。美術館側は快諾してくれ、早速、バーミンガムに会場を下見に行った。美術館のスタッフと小さな動物園に行ったのだ。ぼくは鍵盤ハーモニカ(以下、鍵ハモ)を取り出し、動物たちと共演することが許可された。動物たちの顔色を伺いながら、恐る恐る演奏をする。ヤギがおどおどしながら、音に反応する。鳴き声などで反応がある動物もいれば、その微妙な表情がなんとも言えない動物もいる。これは、音だけではなく映像としても記録すべきだと、直感した。そこで、即興的な音楽を抜群なセンスでドキュメントする映像作家の野村幸弘に、映像記録を依頼することにした。
4 映像作品「動物との音楽」
すると、野村幸弘から逆に提案があった。イギリスに行く前に、日本でも試しにいくつかの動物とのセッションを映像に収めてみようというのだ。
まず、岐阜大学のキャンパス内にいるカモと鍵ハモで共演を試みる。カモの演奏しているリズムを真似してみたりするが、これでコミュニケーションになっているかは微妙。カモはある程度警戒して距離を取るが、遠くに逃げ去るわけでもない。こちらの様子に興味もあるが、不用意に接近するのも危険だという判断だろう。手探り状態の中、映像作品「カモとの音楽」の撮影が終わる。
続いて、畜産センターに行って、ブタとセッションすることにした。再び、ブタの鳴き声、鼻を鳴らすブヒブヒという音を、鍵ハモで模倣してみる。単に真似をすると表面上やりとりしているようでもあるが、これで本当にいいのだろうかと思えてきて、方針を変えてみる。ブタに訴えかけるつもりで、心を込めてメロディアスな演奏をしたのだ。相手がブタだからとか、人間だからという違いを考えず、ただただ無心で演奏したのだ。すると驚くことに、ブタはぼくの方に寄って来たのだ。ブタに媚びて、変にブタの真似をするのではなく、人間は人間の音楽を、ブタはブタの音楽をしながらコラボレートする方が本来の姿なのではないか、と思えてきた。
そして、味をしめたぼくは、さらに別の草を食べるのに夢中なブタに、「おーい、こっちを向いてよー」というメッセージを送るつもりで、演奏した。もちろん、そんなものが通じると思ってやったわけではない。ところがである。2頭のブタが同じタイミングで顔をあげ、同じタイミングでこちらに寄って来て、そして、同じタイミングで顔をこちらに、ふいっと向けてきたのだ。ブタと通じ合ったではないか。歓喜するぼくが、さてこの後、どうやってブタと関わっていこうかと考えた瞬間、ブタたちは何事もなかったかのように、餌に戻って行き、二度と振り向くことはなかった。あの一瞬の達成感の後、どうにも超えられない壁に無力感を覚えた。しかし、この伝わる、伝わらないの微妙な境界が味わえて、ますますぼくは深みにはまっていくことになる。
その後は、まずは色々な動物との共演を経験していこうと思った。Ikon Galleryの企画で、「ウマとの音楽」を撮影した。ウマは鳴いたり、音を出したりはほとんどしなかったが、鍵ハモに強い好奇心を示し、ウマの歩くリズムと鍵ハモの掛け合いのようなセッションにもなった。また、Ikon Galleryでは「カモとの音楽」、「ブタとの音楽」を上映し、さらには、ペットを連れて来てよい音楽会「Music with Pets」を開催した。犬が亀に興奮し、その間を制するように鍵ハモを置くと、犬はそれでも前進しようと、鍵ハモの鍵盤を演奏した。亀は動じることなく、ゆっくり歩き続けた。
「Music with Pets」に触発されて、The Grundy Art GalleryがBlackpool Zooで、動物園の動物とのセッションを設定してくれた。ぼくは、カンガルー、ミーアキャット、ウサギ、ロバなどの動物たちに向けて、鍵ハモを演奏した。いずれも初顔合わせといった感じで、動物たちは様子を伺い、ぼくは手探りで鍵ハモを演奏する。そんなやりとりだった。また、林加奈さんが玩具楽器で共演してくれたが、人間と動物の両方と同時にセッションすると動物だけに焦点が合わせられない。その段階ではないと判断し、それ以降は、再び単独で動物とセッションすることにした。
そんな時に、よこはま動物園ズーラシアの飼育係をしている長倉かすみさんと出会い、「横浜トリエンナーレ2005」で、映像作品「ズーラシアの音楽」を発表することになった。シシオザル、ドゥクラングール、オランウータン、インドライオン、オオアリクイ、ニホンザル、ウミネコ、オットセイとのセッションが映像作品化された。動物に音楽を聴いてもらうことはできたし、動物と音楽を演奏するということも少しだけ実現したと思う。特にオオアリクイは、あの長い鼻でぼくの鍵ハモを演奏し、鍵盤をよだれいっぱいに濡らしてくれた。しかし、「動物と音楽を作曲する」というのは、ある動物と時間をかけて信頼関係を築きながらやれば、実現するかもしれない。それは、まだまだ先になりそうだ。
5 セッションから採譜へ
「動物との音楽」から派生したことに、映像から採譜する作曲法がある。2004年、タイのマヒドン大学の作曲科の大学生・大学院生にレクチャーをした時、映像作品「ウマとの音楽」を見せた。すると、学生からこんな質問が飛び出したのだ。
「この曲は一体、誰が作曲したのですか?」
一瞬、質問の真意が分からなかった。映像の中でウマはほとんど音を発していない。こちらの様子を見て反応してはいるが。だから、映像の中で流れる音楽は、ぼくが即興で演奏した音楽(と環境音)だけだ。だから、この映像に流れている音楽の作曲者はぼくだ、と普通は発想する。ところが、その学生はこう言ったのだ。
「確かに、ここで演奏されている音楽は、全て野村誠さんの即興演奏ですが、それを映像上で編集して構成したのは、映像作家の野村幸弘さんです。作曲するとは、compose(構成する)だから、この曲の作曲者は野村幸弘さんでもあるのではないですか?」
なるほど、もっともだ。幸弘さんは作曲しているつもりなどなく、映像的に面白い場面をつなぎながら、映像作品「ウマとの音楽」を編集した。ところが、そうやって編集した結果、音楽の展開するタイミング、構成などが決定されていくのだ。
確かに、この音楽は映像の論理で展開している。その構成は、音楽家の発想とは少し違う。音楽的に自然な流れならば、あるフレーズを数回繰り返して盛り上げないと次に移れない場面でも、映像だと容易にフェイドアウトしたり、カットアウトして別のシーンにつなぐことができる。突然、場面が切り替われば、唐突に全く違った曲調に瞬時に切り替わっても、違和感がない。「ウマとの音楽」は映像の論理で構成された音楽作品だったのだ。
ならば、この映像論理で展開していく音楽のストラクチャーを生かしたコンサートピースを作ってみようと考えた。ぼくは「ウマとの音楽」を、映像からほぼ忠実に楽譜化した。そして、それをアコーディオンとピアノの2重奏の作品として、書き直した。書き直す上で考えたことは、二つ。一つは、もとの展開の構造は忠実に、映像の論理で音楽が進んで行くようにすること。もう一つは、原曲の即興パートは主にアコーディオンに置き、今回新たにピアノパートを書き加え、原曲のイメージに囚われない新しい音楽を生み出すこと。こうしてアコーディオンとピアノのための「ウマとの音楽」(2005)が生まれた。これに味をしめたぼくは、「ズーラシアの音楽」全曲をアコーディオンとピアノ版として作曲し、山下残演出のダンス公演「動物の演劇」の音楽として発表した。また、演奏会用に「動物の演劇組曲」(2007)として完成させた。さらには、アコーディオンソロ曲として、「ブタとの音楽」(2007)を作曲した。こうして、映像作品から新たにコンサートピースを作曲する手法が確立した。
それならば、コンサートピースを作曲するために映像を撮影する、というプロセスがあってもいいのではないか。そう考えて、ぼくは「べルハモまつり」(2009)を作曲した。「べルハモまつり」は、世田谷区立烏山小学校のつくし学級で行われたワークショップの記録映像から、ぼくが抽出したフレーズを採譜し、再構成して作曲した音楽だ。
ぼくは一巡して、メシアンが鳥の鳴き声を採譜して再構成して作品を書いた方法に逆戻りしたようだ。知的障害の子どもたちの即興演奏のビデオから採譜して、再構成して作品を書いていたのだから。そうか、ぼくはもう一歩踏み込むべきだったかもしれない。知的障害の子どもたちの即興演奏のビデオから採譜して再構成した作品を、知的障害の子どもたちと共演できる作品として作曲すべきだったのかもしれない。次は、そんなことを目指してみたい。
(注:ちなみに、「ウマとの音楽」の作曲者のクレジットは野村誠とし、野村幸弘編集の映像を下敷きにしていることを譜面に書き添えた。)
(次回へ続く)
2009.4.10 update
