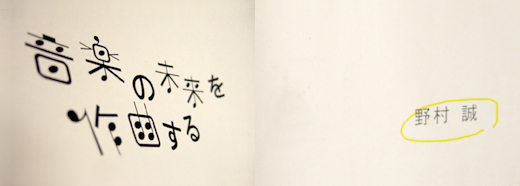
1 室内楽と野外楽
室内楽(chamber music)という言葉がある。弦楽四重奏、ピアノトリオなど、小さな部屋で演奏できる編成の音楽のことを室内楽と言う。オーケストラなど大編成のアンサンブルと対比して使われる言葉だ。でも、「室内」と対比する言葉は、どう考えたって「野外」だ。だったら、「室内楽」と対比すべき音楽は「野外楽」ではないか? ところが、作曲家の作品リストを見ても、「室内楽」はあっても「野外楽」なんて出てこない(ヘンデルの「水上の音楽」、「王宮の花火の音楽」など、例外はあるけれど)。
オリヴィエ・メシアンは、森の中に出かけて、鳥たちが奏でる野外楽を鑑賞し、その音楽を採譜して作曲に応用していた。しかし、実際にメシアンが作曲する音楽は、室内で演奏することを前提にした音楽で、野外楽を作曲することはなかった。また、ベラ・バルトークは、トランシルバニアの山中に出かけて、多くの民族音楽を採集した。その中には野外楽が数多くあったに違いない。しかし、バルトークが作曲する音楽も、室内で演奏する音楽で、野外楽は作曲していない。現代の作曲家は、野外楽の作曲に、もっと積極的に取り組んでもいいのではないか。実際、民族音楽の中には、野外で演奏するものが極めて多いわけで、そもそも野外は音楽に満ち溢れている。ぼくは、室内だけのために作曲するのではなく、野外楽も作曲したいと思う。
野外楽の作曲への手がかりは、野外に出かけ、野外で演奏してみることだ。試みにおもちゃのピアノを持って、近所を散歩する。外の風は気持ちいい。しかし、京都の街を歩いて行くと、自動車のエンジン音が、かなりうるさい。おもちゃのピアノの微細な音色は、自動車の低音に見事な程にマスキングされてしまう。室内でのコンサートでは、屋外のノイズや環境音は遮断され、楽音だけが聞こえてくるが、野外では、あらゆる環境音が聞こえてくる。だから、微弱音の楽器は、野外楽には向かないことが多い。だから、そうした環境にも耐えうるだけのパワーがある楽器(例えば、和太鼓など)が、しばしば野外楽で用いられるのだろう。
野外楽で効果満点だった和太鼓を、非常に残響のあるコンサートホールに持って行く。今度は、壁からの反射音が強すぎて、はっきりとリズムが聞き取れない。ウワンワウンと響いて、何が何だか分からなくなってしまう。音が耳に突き刺さって痛い。音の逃げ場がないのだ。同様に、野外を前提としているバリ島の楽器ガムランも、コンサートホールでガンガン鳴らすと、響き過ぎて、音の粒が聞こえてこなくなってしまうことがある。野外では反射が少なく、四方に音が拡散する。そのために、直接音がより明確に聞こえてくる。室内では、壁があるために直接音と間接音が、時に干渉して、響きを濁らせてしまう。
室内に適した楽器、野外に適した楽器というのがあるのかもしれない。ホルンという楽器は、室内で演奏すると、部屋自体を響かせて独特な豊かな響きが出るのに、反射する壁がないと、途端に貧弱な音色になってしまう。
野外楽を探求するため、杉岡正章鶴、山下残との野外での歩行器プロジェクト「バレエ」(1993〜)、美術家の島袋道浩との「路上バンド」(1993〜)を開始した。野外で演奏していると、見ず知らずの人から急に話しかけられたりする。ぼくは、路上演奏で人と交流することの面白さに強く興味を抱き、路上演奏に没入していくことになる。1999年にCDブック『路上日記』(ペヨトル工房)を上梓するまで、ぼくは人との出会いに重点を置いた野外楽「路上演奏」を集中的に行うことになる。
2 火の音楽会
路上演奏では、人との交流に重点があった。しかし、もっと環境との交流、野外ならではの音楽がしてみたい。そう思うようになったぼくは、豊科北小学校校庭、佐倉城址公園、牛窓山頂、蒲郡の海岸など、野外でしょうぎ作曲を行った。しかし、もっと踏み込んだ野外楽がやりたい、そう考えていた2004年、野外ならではの音楽をする大きなチャンスが訪れた。神戸の六甲山にある神戸市立自然の家で行われる「ネイチャーアートキャンプ2004」で、ワークショップを依頼されたのだ。六甲山の自然の中で、小学生を対象にした音楽のワークショップをして欲しいという。ぼくは六甲山に下見に行き、広大なキャンプ場で音楽をすることに心を時めかせた。下見をしているうちに、ぼくはキャンプファイヤー場に辿り着く。そして、「火」を主役にする音楽会をしたい、と思いついた。
物が燃える音は、非常に複雑で繊細で美しい。ぼくは、火の奏でる音楽が大好きだ。ぼくが子どもの頃に体験したキャンプファイヤーでは、火の周りでゲームをしたり、歌を歌ったり、寸劇をしたりした。しかし、中央でせっかく火が音楽を奏でているのに、その音楽を聴かずに、周りで人間が騒ぐ。そうではなく、キャンプファイヤーの火が奏でる音を主役に据えて、音楽を作曲できないか。
とは言うものの、ぼくは火という楽器に対して、あまりにも未熟で初心者だ。「作曲する遊び場」という精神でいけば、未熟であろうが初心者であろうが、遊びながら発見していけばいい。しかし、火を扱うということは、安全管理が非常に重要になる。まずは、吉長成恭・関根秀樹・中川重年編『焚き火大全』(創森社)を購入し勉強をする。しかし、本の上で勉強しているだけでは、実践が伴わないので、キャンプファイヤーの経験豊富なボランティアのスタッフとともに、何度もキャンプファイヤーの練習をすることにした。キャンプファイヤーの練習をするために、何泊もキャンプをした。木が燃える音、葉っぱが燃える音、微妙に違う様々な音を確認すると同時に、安全性/危険性を確認しながら進めていく。そして、以下のようなアイディアで、「火の音楽会」を構成した。
(1)線香花火オーケストラ ボランティアの学生からは、手作りで線香花火が作れるというので、線香花火50〜80本を同時演奏することに
(2)火打石のアンサンブル 子どもたち全員と石を鳴らしながら、火花を飛び散らせる
(3)聴診器で火の音を聴く 燃えている火の中の音を聴く、特性の聴診器(注1)で火の中の音を聴く
(4)マイクで薪が聴いている音を聴く キャンプファイヤーの薪に特性のマイク(注2)を設置し、薪が聴いている火の音をスピーカーで増幅して流す
(5)鉄板のデュエット 火で熱した鉄板にやかんで水をそそぎ、水のそそぐ量で「じゅーーーーー」「じゅっ」とリズムに変化をつける合奏
(6)火の四重奏 4つの焚き火に一奏者がつき、枯れ葉、水、鉄粉、オイル、、、様々なものを加えながら、合奏
(7)火によるピアノ演奏 廃棄処分になったピアノに点火し、ピアノの燃える音を聴く
「火の音楽会」は、音に重点的にフォーカスを当てたコンサート・ワークショップとして構成したが、火の燃える様子、火の温度、10月の夜の肌寒さ、煙の匂いなど、視覚、触覚、嗅覚など、全感覚に訴えてくる体験だった。野外楽は、室内の音楽に比べて、聴覚以外の感覚に訴えてくる部分が圧倒的に大きかった。野外楽を続けると、音楽とは耳で聴くだけのものではないと確信するようになった。
聴覚障害児との音楽活動を続ける作曲家の佐藤慶子に、『五感の音楽』(ヤマハミュージックメディア)という著書がある。また、小松正史は、自身の研究分野をサウンドスケープではなく、「五感環境学」と呼んでいる。音を視ることを、音を触ることを、音を味わうことを、音を匂うことを忘れてはいけない。音楽は五感で感じるものだ。いや、ぼくらには第六感もある。第六感も含めた全感覚を通して音を体感する、その行為こそ音楽と呼ぶべきではないか。野外楽の作曲を探求していく中、ぼくにとっての「音楽」の定義は、音を耳で聴くことを超越し、音を全感覚で体感する行為になったのだ。
定義:音楽とは音を全感覚で体感する行為だ(野村誠)
(注1)池田邦太郎さん(当時、奥多摩の古里小学校の音楽教諭)が、小学生と聴診器を作っていたことを思い出し、池田さんに特性の聴診器を依頼した。池田さんは、火から十分距離が保てるように、聴診器にアルミの管が5メートルついたものを作ってくれた。また、冷却用に管の周囲に蛇腹状になった管を重ね、外側の管と内側の管の間に水を入れることにした。
(注2)できる限り安価で入手できるマイクを薪に設置し、それをライブで増幅して聴いてみた。自作のマイクを使って独自の録音の世界を展開している五島明彦さんにお願いした。五島さんは、色々な安価な材料を工夫して、1000円弱のマイクを10本ほど作ってくれた。
3 i-picnic
音楽を「音を全感覚で体感する行為」と定義したぼくは、野外に出かけて、全感覚を総動員して行う野外楽を作曲していきたいと考えるようになった。野外楽を探求するための「作曲する遊び場」が、ぼくには必要だった。ぼくは、野外楽を追求するための新ユニットi-picnicを結成することにした。i-picnicは、improvisation picnicを略して生まれた名前で、野外での即興演奏がその活動の主軸だ。
2004年12月、東南アジアのサウンドスケープ研究家である中川真さん、「場所の音楽」を提唱する映像作家の野村幸弘さんと3人で、タイ(バンコク、アユタヤ)を訪れたのが、最初のプロジェクトだ。バンコクの高層ビルの屋上、アユタヤの遺跡、バンコクの路地などを舞台に、即興演奏を行った。この時、意気投合したタイの民族楽器を演奏するアナン・ナルコンは、第4のメンバーとなった。
2005年5月、第2回目のi-picnicが選んだのは、インドネシアのジャワ島。中川さんの希望で、絶対に車の音が一切聞こえない場所を現地の音楽家に探してもらったところ、標高700mの山の上ポンジョンに行くことになった。
中部ジャワにあるジョグジャカルタから、舗装された道を車で2時間ほど行った後、さらに舗装されていない道を2時間近く進んだ先が、ポンジョンだ。車が辿り着いたのが、ポンジョン最後の民家の前。ここで、食事をお世話になることに。そして、そこからさらに、草をかき分けながら、歩いて行くと,崖の上に出る。信じられない絶景がある。崖の下を見下ろすと、約100mほど下に、集落が見える。そこにテントをはり、3日3晩、朝から晩まで、即興音楽を続けた。野村誠、野村幸弘、中川真、アナン・ナルコンに加えて、ジャワ舞踊の佐久間新、ガムラン音楽家のヨハネス・スボウォが新メンバーに加わった。
鍵盤ハーモニカを持ってポンジョンでの即興演奏に加わったぼくは、最初、大いに戸惑った。鍵盤ハーモニカは西洋音楽の12平均律に調律されている。ところが、アナンの持参したタイの楽器は、1オクターブを7等分した7平均律に調律されている。さらに、スボウォ、中川真が持参したジャワのガムランの楽器は、1オクターブを五等分しているスレンドロという音階だったりする。この3つの全く違った音階が同時になっている。ぼくには、3つの異なる音階が共存する中で、どの音を吹いても、何か馴染めないような気がして、模索の連続だった。でも、音楽は「音を全感覚で体感する行為」なのだから、音律については考えないようにして、ただ、全身で音を感じようとした。日本とは全く違う鳴き方で、ジーワンジーワンと蝉が鳴いている。心地よい風が吹き、木々がざわめいている。ぼくは、アナンやスボウォと演奏しているだけではない。蝉とも、風とも、この場にある全てのものと共演している。インドネシアの音階、タイの音階、西洋の音階など、人間が作った枠組みに囚われている自分は、音を音そのものとして味わっていない。音に名前をつけることをやめて、全ての音にニュートラルに向かう。そこには、音がある。色んな音が鳴り響いている。それに、何かを感じて、自らも音を発したい衝動に駆られる。そして、音を発する。ただそれだけだ。
ぼくは、徐々に自分の概念化された耳から解放されて、音律などについて気にせずに鍵盤ハーモニカを演奏できるようになっていった。鍵盤ハーモニカだけではなく、風、葉っぱ、石、田んぼ、用水路の水、あらゆるものと対話を交わし続けた。
その後も、i-picnicは、2006年8月に第3回(日本)、2007年10月に第4回(オーストリア)、2007年11〜12月第5回(タイ、カンボジア)と場所を変えて開催している。
4 企画譜と報告譜
「火の音楽会」では、実際に進行表を作り構成を決定していった。ぼくにとって、「火の音楽会」を作曲するというのは、企画書を作成しているような気分だった。これから起こるであろう出来事を想定し、どのように進行するかを記した楽譜を、「企画譜」と呼んでみよう。「企画譜」は実施以前に作成するので、実際にはどうなるかは、やってみないと本当のことは分からない。もちろん、以前に経験したことに類似した企画であれば、だいたい想定もつくだろうし、全く初めてに近いことになればなるほど、企画譜の段階では未知数の部分が大きい。例えば、「火の音楽会」では、線香花火を80本で合奏する音は、「企画譜」の時点では、実際の音や情景は想像がつかなかった。また、ピアノに火をつけた時に、琵琶のようなベベンという音で弦が切れるのも、やはり想定できなかった。これらは、ぼくが体験してみたい未来を記述する楽譜で、実際の演奏は、常にぼくの想像を超えたところに到達する。
では、「企画譜」の反対は何だろう? 事業を実施する前に書くのが企画書ならば、事業を実施した後に書くのは「報告書」だ。では、「報告譜」という概念を考えてみよう。例えば、「ウマとの音楽」は、もともとバーミンガム郊外の牧場での即興演奏だったが、映像ドキュメントから譜面を書き起こし、「報告譜」を作成した。また、ヒュー・ナンキヴェルと佐久間新と深谷保育園の園児の即興演奏は、「キーボード・コレオグラフィー・コレクション」のやわらかい楽譜という「報告譜」になった。ただし、「報告譜」を、単に過去の結果を追体験するだけのものにしてはもったいない。実際に行われたことの中からエッセンスを抽出して、新たな音楽を生み出すための有効な方法として機能させたい。そう考えた時、ぼくはまだ、i-picnicを「報告譜」として譜面化していないことに気づく。今後、i-picnicを「報告譜」として楽譜化し、再演をしていく作業が始まるだろう。インドネシアの野外で行った音楽を、ヨーロッパの田舎で再演する場合など、環境が変われば、その状況に適応させる必要も出てくるだろう。そうやって土地から土地に移動しながら、音楽は変化していくだろう。
こうして野外楽を経験した上で、もう一度、室内に戻ってみる。第6感までを含めた全感覚で音を感じてみる。冷蔵庫のブーーンという音、流しの水の流れる音、時計の秒針、至る所に音楽が満ちあふれている。楽器もいっぱいある。本、ペットボトル、紙、たわし、ボウル、など、身の回りには音を発するものが無限にある。ジョン・ケージに「居間の音楽(Living Room Music)」という作品があるが、野外が音の宇宙であったように、室内も音の宇宙だ。そうした音の世界の可能性を、2006年NHK教育テレビの音楽番組「あいのて」として提示した。現在は、バンド「あいのてさん」として、「ペットボトル・メモリー」、「イシ・テクノ」、「レッツゴー・レジぶくろ」などの作品として展開している。
注
ちなみに、「企画譜」と「報告譜」と酷似した概念に、「規範的楽譜(prescriptive notation)」と「記述的楽譜(descriptive notation)」がある。柿沼敏江は『アメリカ実験音楽は民族音楽だった』(フィルムアート社)の中で、アメリカの音楽学者チャールズ・シーガーの用語として、
「規範的楽譜 prescriptive notation」とは、音楽がどう鳴るべきかを示す青写真としての楽譜であり、「記述的楽譜 descriptive notation」は、ある音楽の特定の演奏が実際にどう音になったか報告する楽譜である (p.256)
と説明している。
(次回へ続く)
2009.6.12 update
