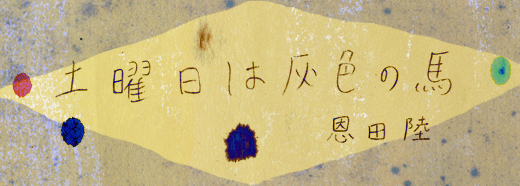
(1)
小説家には、仕事のやり方においていろいろなタイプの人がいる。
私には絶対できないのが、「毎日一定量を必ず書く」というのと、「連載小説をまとめて渡す」というタイプの仕事である。
特に、いつも見切り発車で連載を始めている私にとって、「連載小説をまとめて渡し、分載してもらう」というのは考えられない(いや、本当は、一度でいいから、そういうことをやってみたいのである。「はい、一年分」と涼しい顔でどーんと渡せたら、どんなに気持ちいいだろうなあ。昔はある程度書き溜めてから連載をスタートしていたのだが、現在は、単に仕事が遅い上、スケジュールが常に押しているので、連載開始時までに書き溜めるのが間に合ったためしがないのだ)。
直接聞いたわけではないので分からないけれど、そういうタイプの人は連載十二回なら十二回分区切って渡すわけではないらしく、あくまで「書き下ろし一冊分」を渡して編集者に分載してもらうらしい。
これが私にはできない。書き下ろしは書き下ろし、連載は連載、だ。「連載」というからには「連載」なりの見せ方があると思う。やはり、ライブ感、疾走感がそれなりに必要だと思うのだ。
同じ話を連続ドラマ化するのと、映画化するのでは、観客に対する戦略が全然違う。当然ながら、情報量と、その情報の配し方が異なってくる。五十分ドラマを四回だったら、毎回それぞれに起承転結があって、導入のつかみ、後半の見せ場、更に次回への期待を持たせるラストを持ってこなければならない。
特に私にとって、「次回への期待=引き」はほとんど身体の奥に染み付いていて、例えば一回三十枚の連載ならば、二十七枚目くらいになると、無意識のうちに「嘘だろ、この先いったいどうなるわけ?」という展開になってしまう。白状すると、時には、「おい、こんな展開にして、次回どうやって解決するつもりだ、おまえ?」と自分に突っ込みを入れてしまうほど、解決する見込みもない癖に「引き」だけは確保してしまうのだった。もちろん、何も考えずに反射のみでやっているので、「次回」以降、辻褄が合わせられなくなり地獄を見る。
ただ、「引き」を作るにはある程度の長さが要る。
昨今、活字媒体は文字が大きくなっているので、容量は以前より減っている。
週刊誌連載の場合で、通常、一回約十五枚である。それでも、十五枚あればなんとか毎回それなりに見栄えのする「引き」が作れるが、困ったのは新聞連載だった。一回、二・五枚しかないのである。さすがにこの長さで毎回「引き」を作るのはあきらめざるを得なかった。だが、それでもなんとか期待を持たせられないかと、既に遅れまくっているくせに往生際悪く毎回しつこく粘ったことを覚えている。それほど、私の「『引き』を作らなければ」という強迫観念は強い。
(2)
こうなった理由は、分かっている。
子供の頃に浴びるほど読んでいた漫画雑誌のせいだ。
今は単行本になってから読む人が多くなったというが、かつて漫画というのは「連載」で読むものであった。連載漫画の「次号へつづく!」がどんなに恨めしく、どんなに憎かったことか!!
なにしろ、いっときは「なかよし」「りぼん」「花とゆめ」「別冊マーガレット」「週刊少女フレンド」「週刊少年チャンピオン」「週刊少年マガジン」「週刊少年サンデー」を並行して読んでいた私である。「次号へつづく!」への恨みと焦燥も、人一倍刷り込まれているのである。
『恐怖新聞』『魔太郎がくる!!』『ブラック・ジャック』あたりは一応毎回読みきり形式になっていたからよかったものの、『ドカベン』とか『イヤハヤ南友』とか『おれは直角』とか、「どうして毎回こんないいところで終わるわけっ? キーッ!」と文字通り地団駄を踏んでいた。
今でも最大(最悪)の引きの強さで覚えているのは、忘れもしない『愛と誠』である。
思い出しても身もだえする魔性の引き、『愛と誠』。
知らない方のために言っておくと、要は超お嬢様と超不良の純愛物語である。子供の頃、スキー場で暴走した早乙女愛を身体で止めてくれ、愛のスキーの先端で額に三日月形の傷を負ったのが運命の人、誠なんなんである(あれ? 誠の苗字、なんだっけ。あ、太賀か)。ついでに言うと、女優・早乙女愛は、『愛と誠』で映画デビューした時にそのまま役の名前を芸名にしてしまったんである。
なにしろ、引きは凄いんだけど、いっこうに話が進まない。単行本は全部で何冊になったのか忘れたが、一冊読んでもほとんど話が進まないのである。なのに、凄い引き。恐るべし、『愛と誠』はほとんど「引き」だけの話だったのだ。
高橋留美子が『うる星やつら』で登場した時も衝撃的だった。パワフルでエネルギッシュで何よりスピーディー、次々登場するキャラクターは綺羅星のごとく魅力的、しかもアイデア満載で密度が濃く、凄まじいインパクトがあった。あんな凄い話を毎週描いてたなんて、本当に信じられない。
意外に(というのは失礼かもしれないが)凄かったのは里中満智子だ。少女漫画のストーリーで「引き」を作るのは結構難しいと思うのだが(昔、いっとき流行した「バレエ」プラス「出生の秘密」みたいなのは別として)、『アリエスの乙女たち』の「引き」は凄かった。漫画界屈指のストーリーテラーだと思う。『アップルマーチ』とか『恋人はあなただけ(これの展開もさりげに凄かったぞ)』も好きでした。
そして、「引き」の真打ち、美内すずえ。『ガラスの仮面』は、最初は月刊だった「花とゆめ」の月二回刊化の記念連載だった。はっきりいって、全ページ暗記している。「逃げた小鳥…」「おらぁトキだぁ」「毒…ここにいるのは審査員という名の観客」毎回毎回、どれも皆「引き」の嵐で、思い出しても眩暈がするほどだ。
うう、美内先生、私はあなたの『ガラスの仮面』を読んでこんなに立派な「引き」命の女になりましたあ。
子供というのは、一日一日が長いもの。月刊誌の発売日なんて、絶望的に待ちきれなかった。今でも覚えているけれど、小学生時代、富山の駅前の小さな本屋さんが発売日でなく配本日にこっそり内緒で雑誌を売ってくれる、というのをやはり私と同じ少女漫画オタクの同級生から聞いて、母親と一緒に行って無理やり「りぼん」と「なかよし」を発売日前に売ってもらったことを覚えている。しかし、楽しみにしていたので凄い勢いで読み終えてしまい、それからの一ヶ月が永遠に思えて、「オーマイガッ!」と毎回天を仰いでいたのだった。
ようやく理性的に次の発売日が待てるようになったのは、高校生くらいになった辺りである。「いい加減に漫画は卒業しなさい」と小学校六年くらいから母親に囁かれ続けてきたのだが、なにしろ「花とゆめ」の次に「LaLa(らら)」とか「ぶ〜け」とか出来て、少女漫画の進化が一段と凄味を増していた時期だったので、無理でしたねえ……
(3)
そう、「連載」が日本の漫画を鍛えていたことは間違いない。いかに読者を飽きさせないか。いかに読者を繋ぎ止めるか。いかに驚きのストーリーを展開させるか。それを週一、せいぜい月一というほぼリアルタイムで持続させるのだから、まさに漫画家と読者の死闘である。それは現在も続いている……うーん、偉いなあ、ほんとに。
中でも、「連載」でなければ絶対にありえなかっただろうなと思う作品のひとつが、一条ゆかりの大長編、『砂の城』である。
作者は「とにかくメロドラマが描きたかった」と語っているが、とにかく最初の三回の展開が凄まじい。
大河ドラマの導入部に当たるのが最初の三回で、三回目の最終ページで物語の骨組みが明かされるまで、この骨組みを想像できた読者はまずいなかったのではないかと思われる。いや、それどころか、第一回を読んで第二回の展開、第二回を読んで第三回の展開を予想することすら難しかったと思う。
もしこれが読みきりだったら、導入部がここまでドラマチックな展開にはならなかったはずだ。また、この話が小説や映画だったら、このようなストレートな進行にはせず、絶対にカットバックで語り手が回想する形になっていたに違いない。連載漫画という形式だったからこそ、こういう展開になったのだ(←気になる人は、是非原典を当たるように。私としては、この導入部を読む楽しみと驚きを奪うことは遠慮したい←といっても、実は以前よその原稿でばらしたことが……すみません、反省しています)。
そして、もうひとつ。
私の脳内史上最も凄かった「引き」は、山岸凉子の代表作『アラベスク』第一部を「りぼん」に連載していた時の、ある回のラストシーンである。
『アラベスク』は、「見えない天才」であるバレリーナ、ノンナ・ペトロワを主人公とする物語である。ソビエト連邦の田舎のバレエ学校の劣等生だったノンナは、レニングラードバレエ団のスターダンサー、ユーリ・ミロノフに見出され転入するが、本人の気の弱さが災いして、主役争いに敗れてしまう。
彼女は居場所がなくなって逃げ出してしまい、それでも地方の小さなバレエ劇場に清掃員として潜り込む。偽名を使っているが、彼女を受け入れた老プリマは彼女の正体を見破っており、自分が怪我をした時の代役に彼女を指名する。
しかし、バレエ団員たちから老プリマは反感を買っており、彼女の相手役となったダンサーは舞台の上で彼女を転ばせようとするのである。
たまたま客席では、ノンナの郷里でバレエ教師をしている母親らと知り合いだった、やはりプロのバレエダンサーであるタチアナが観ている。彼女は地方公演のついでに寄ったのだが、踊っているノンナを観て、その踊りに見覚えがあることに気付き、相手役のダンサーがノンナに悪意を持っていることを見抜いて憤る。
ノンナの中にふつふつと込み上げる、これまでに感じたことのない激しい怒り。恐らくは事実上の引退になるであろう老プリマの最後を踏みにじろうとする者に対する怒りと、観客を無視して自分たちの不満を晴らそうとする者たちへの怒りである。
そして、彼女は相手役のサポートを拒絶し、たったひとりで毅然と難しい決めのトウのポーズに挑むのだ。
最後のシーンは、呆然とする相手役を残してノンナが一人でポーズを取っており、驚愕したタチアナが「あんなことができるのは確か……」と叫ぶシーン。
いやあ、今思い出しても興奮しますねえ。
ついでに言えば、このページの下に「りぼん×月号につづく」という文字を見た時のショックと恨めしさも。
「なんでまた、よりによってこんなところで『つづく』なわけ? 殺生なっ! あんまりだっ! キーッ!」
ああ、歳月を超えて、やはり叫んでしまうのである。
けれど、こうやって地団駄踏んで、お話の続きに恋い焦がれることくらい、楽しいことはないことも、今なら知っているけどね。
なにしろ、「引き」は「連載」の何よりの醍醐味なのだから。
(2006.10.30)
