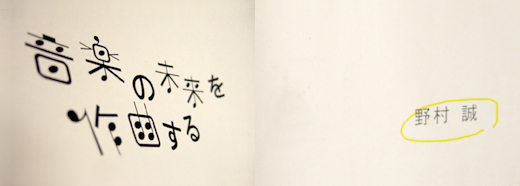
1 音楽の過去を作曲する
過去を掘り下げる活動が、「報告譜」や「ポスト・ワークショップ」だった。「報告譜」は、自分の既に行った過去の即興演奏などを記述する楽譜だ。その記述の方法が不完全であれば、過去に実在した音楽とは全く違った音楽が生まれてしまう。また。「ポスト・ワークショップ」では、過去のワークショップで起こった出来事から、創造の種を発掘し、そこを起点として作品を作っていく。その結果、ワークショップでは想像もし得なかったような作品が生まれてしまうのだ。既に過去に実在した音楽(ワークショップ)を記述することで、その過去に存在したものとは、全く別の音楽が浮き上がってくるところが面白い。
例えば、野村誠とヒュー・ナンキヴェルの「キーボード・コレオグラフィー・コレクション」は好例だ。このプロジェクトは、子どもがピアノを自由に演奏する様子を観察し、それを振付として記述する、というもので、それぞれの振付を、文章で「報告譜」として記録した。ジャワ舞踊家の佐久間新さんをゲストに迎えた2009年1月のコレクションでは、50の技法を収集したのだが、その中でも、第48番の「振り子奏法」は、ポスト・ワークショップで大きく展開した。
KCC48(振り子奏法) ピアノ椅子に座って、足を浮かせて、振り子やシーソーやブランコのように、前後に揺れながら、演奏する。前に来た時は鍵盤に触るが、後ろにふられる時は、鍵盤から手を離す。これを続ける。
実は、この「振り子奏法」は、ワークショップの最中は、誰も自覚していなかったのだが、野村、佐久間、ヒューの3人でワークショップの記録映像を分析していた(ポスト・ワークショップ)時に発見された。微かに子どもが仰け反った動作に着目し、それを文章で強調したのだ。佐久間新さんが、この奏法を極端にまでゆっくりとした動きでやってみると、動きとしても美しいのだが、音としても美しい。ダンスと音楽が美しく融合していることに、ぼくらは歓喜した。
佐久間さんは、さらにポスト・ワークショップを深め、その後、「振り子奏法」に基づくガムラン作品「SANZUI」を発表したり、クレムス(オーストリア)での現代音楽祭などで、ソロピアノの振り子演奏も続けたりしている。もちろん、ぼく自身もピアノの振り子奏法ソロを何度も試みているし、さらには、演じるバンド「門限ズ」で、振り子奏法のトリオとして上演してみたりもした。こうした振り子奏法の「ポスト・ワークショップ」的な展開は、当初のワークショップで存在していた音楽に起点を起きつつも、振り子的なゆったりした動きが大きく強調され、新しい作品になっている。ぼくは、こういう創造的な逸脱が起こるところが、ポスト・ワークショップの面白さだと思う。
こうして、既に行われた過去のワークショップを掘り下げるポスト・ワークショップを続けると、次々に新作が生まれてしまう。新作を作るために新しい企画を考案するのではない。ただただ過去に実在した音楽(ワークショップ)を丁寧に観察・分析しているだけなのに、新作や新企画が生まれてくるのだ。何と逆説的なことだろう。過去を掘り下げれば、未来につながるのだ。過去の作品を真剣に記述していけば、自ずと新作が生まれてしまうのだ。
では、同様に、自分の過去ではなく、自分以外の過去を題材にしてみてはどうだろう? 丁寧に観察・分析していくだけで、新作が生まれてくるのだろうか?
2 北斎漫画の四重奏
過去の作品を掘り起こし、それを観察・分析・記述することが新作につながること、これを仮に、「考古学的な作曲(archeological composition)」と呼んでみよう。考古学的な作曲と言えば、フランスの作曲家オリヴィエ・メシアンの名前が浮かぶ。メシアンは、13世紀のインドで書かれた音楽理論書(サールンガデヴァ著「サムギータ・ラトナーカラ」)をもとに、かつて存在したかもしれない当時のインド音楽のリズムを(彼なりに)学び、自身のリズム理論(「逆行不可能のリズム」、「リズムの拡大・縮小」、「付加されたリズム」)などを編み出した。メシアンの音楽のリズムは、当時のインド音楽を復元しているとは思えないが、本人が敢えて曲解したようでもない。当時の音楽を記述する情報が不十分であるために、新しい音楽が生まれてしまったのだろう。古文書の少ない情報を手がかりにして生まれたメシアンの音楽は、考古学的な作曲の好例と言えるかもしれない。
ぼくにとっての「考古学的な作曲」の題材は何がいいだろうか? 東大寺大仏開眼会(752)の音楽を聴いてみたい。世阿弥の能を見てみたい。江戸の歌舞伎を見てみたい。とにかく、日本音楽の様々な時代の音楽を体験してみたい、という思いは強い。その中でも、以前から、平等院の雲中供養菩薩像には、強い関心がある。様々な楽器を演奏している彫刻を見ていると、1000年近く前の日本の音楽が生き生きと想像されてくる。しかも、その演奏している楽器の中には、現存する雅楽とは、随分違った種類の楽器もあり、演奏している様子も、厳かというよりも、自由気ままに見えるのだ。「しょうぎ作曲」をしている人々の様子に似ているのだ。
そんなことを考えている時、葛飾北斎の「北斎漫画」を偶然手にとった。そして、その中に驚くべき四重奏が描かれていたのだ。尺八を吹いている男、琴を弾いている男、胡弓を弾いている男がいる。3人とも胡座をかいて床に座っている。江戸時代らしい光景だ。尺八、琴、胡弓の3人だけならば、ぼくは、別に驚きもしなかったし、何とも思わなかっただろう。ところが、その横に、もう一人、木琴らしき楽器を演奏している男がいて、両手に桴(ばち)を持って、左手を高く振り上げているではないか? おいおい、ちょっと待ってくれ! 江戸時代に木琴や鉄琴があったなんて話、聞いたことないぞ。だいたい、尺八や琴と一緒に、木琴が出てくるような合奏など、見たことも聞いたこともないし、そもそも、木琴の家元とか、木琴の××流というのも、聞いたことがない。これは、一体、何なのか? でも、確かに描かれているのだから、こういう音楽があったのだろう。しかも、その演奏している様子が、まるでジャムセッションでもしているかのような自由な雰囲気なのだ。江戸時代にも、即興音楽は盛んだったのだろうか?
この絵を一目見て、ぼくは、瞬時に木琴だ、と思った。絵だけでは、木琴か鉄琴か竹琴か、材質までは判別できない。しかし、楽器の形状が、インドネシアの木琴(ガンバン)にそっくりだったのだ。江戸時代にインドネシアのガンバンが、オランダ経由で日本に伝わり、ガンバンと尺八や琴とセッションをしていたのだと推測した。きっと、長崎での光景で、長崎に出かけた北斎が、偶然目にしたものなのではないか? ぼくの妄想は膨らんだ。「考古学的な作曲」の題材は、北斎の描いた四重奏に決まった。
3 考古学的作曲の方法
ぼくの新プロジェクト「考古学的な作曲」は、北斎漫画の四重奏になった。幸いにして、2011年に北斎館をオープンする墨田区、地域資源リサーチプロジェクトを模索中のアサヒ・アートスクエアが、「北斎漫画の四重奏」に興味を示してくれた。2009年11月より「野村誠×北斎~江戸時代のworld music!」を開始することができた。「考古学的な作曲」の方法論としては、「キーボード・コレオグラフィー・コレクション」でのアプローチを参考にして、3つの流れを考えた。
(1) データの収集・分析
(2) 実験
(3) 作品
「キーボード・コレオグラフィー・コレクション」の時には、(1)は、深谷保育園で子どものピアノ演奏を映像で記録し、映像を分析して「キーボード・コレオグラフィー」のテクニック、アプローチ、クエスチョンを書き出すことだった。(2)は、書き出したテクニック、アプローチ、クエスチョンを、大人たちと実際にワークショップで実験(実践)することだった。(3)は、そうして実験したテクニックなどをもとに、「SANZUI」などの作品を生み出すことになる。
同様に、「野村誠×北斎」でも、(1)~(3)の流れで進めてみることにした。(1)のデータの収集・分析では、専門家への取材調査を中心に、3回のトークイベントとして開催することにした。「北斎漫画の四重奏」に関する情報を、美術史、楽器学、日本音楽の専門家から聞き取り調査を行い、分析を行った。(2)の実験では、(1)のトークセッションに基づき、実際にワークショップで実験(実践)してみることにした。2回のワークショップを開催し、実際に木琴を製作したり、四重奏で音楽を奏でてみた。(3)は、(2)の実験結果に基づいて、現在、野村誠が作曲中である。この3つのステップは、以下のように言い換えることも可能かもしれない。
(1) プレ・ワークショップ(=トークセッション)
(2) ワークショップ
(3) ポスト・ワークショップ(=作曲、コンサート)
4 5つの謎
3回のトークセッションは、謎を探す旅でもあった。第1回のトークセッションは、日本美術史で北斎の専門である奥田敦子さん(財団法人墨田区文化振興財団学芸員)をゲストに招き、北斎の生涯、北斎の作品などを、初心者のぼくにも分かるレベルから解説していただいた。そして、最後に、「北斎漫画の四重奏」について、奥田さんにも質問してみた。すると、この四重奏を演奏している人の服装などから判断すると、木琴を演奏している人、琴を演奏している人の二人は、視覚障害者のプロの演奏家であるらしい。頭を丸めていることや眼の描き方などから、当道職屋敷(視覚障害者の職能集団)の演奏家ではないか、とのこと。尺八を吹いているのは虚無僧で、胡弓を弾いているのは、何の変哲もない普通の町民以上のことは分からない、とのこと。ここで浮上する謎は、この背景の違う4人が一緒に集まってセッションをする状況があり得たか? また、4人は一体、どんな音楽を演奏したのだろう?
第2回のトークセッションでは、「描かれた木琴 ー江戸時代の木琴をめぐる図像分析試論ー」という論文を発表されている中溝一恵さん(国立音楽大学専任講師)をゲストに招き、江戸時代の木琴にフォーカスをあてた。すると、19世紀の江戸で、木琴がブームになっていたことが分かった。1804年に初演の歌舞伎「天竺徳兵衛韓噺」でのことらしい。越後座頭に扮した天竺徳兵衛が、滝川左京の館に(木琴を背負って)忍び込み、木琴を叩きながら越後節を歌うシーンが出てくるらしい。実際、徳兵衛は怪しまれ詮議にかけられ、前の池に飛び込むのだが、この木琴を演奏するシーンが印象的で、江戸の木琴ブームの火付け役になったようだ。また、北斎以外に多数の浮世絵師が木琴を描いており、そうした図像を多数見ることができた。浮世絵の木琴の中に、用途不明の横棒が付いているものが多数あり、さらには、湾曲した桴が描かれているものもある。現存のインドネシアのジャワ・ガムランには、横棒のついた木琴は存在しないが、20世紀初頭のジャワ・ガムランの写真で、横棒のついた木琴が写っているものがあるらしい。このことから、木琴はインドネシアから日本に伝わったと、中溝さんは推測している。ここでは二つの謎が浮上してきた。どうして木琴には横棒が必要だったのか? そして、どうして、桴は曲がっているのか?
さらに、第3回のトークセッションでは、日本音楽の専門家の茂手木潔子さん(上越教育大学名誉教授/有明教育芸術短期大学教授)をゲストに招き、茂手木さんが、江戸時代より歌舞伎の楽器の貸し出しを行っている老舗「岡田屋布施」に依頼し、歌舞伎で使う木琴を4台貸してもらうことができた。これらの楽器は、浮世絵に登場したのと同じようなサイズで、インドネシアのガンバンに形状は似ているものの、明らかに小さいサイズだった。音階はインドネシアの音階とは全く異なり、チューニングが狂い過ぎているため、音階の規則性も発見できなかった。音色もジャワのような柔らかい音色ではなく、日本独自の硬質な音色だった。また、岡田屋布施の倉庫の奥から、曲がった桴が発見された。浮世絵にあるような湾曲した桴が、確かに実在した。しかし、4台の木琴には、いずれも横棒は存在しなかった。横棒の謎は、さらに深まった。また、木琴がどのような音階であったのかも、謎のままだ。
もう一度、3回のトークセッションで浮上した謎を整理しておこう。全部で5つある。
Q1 どうして木琴の桴は湾曲しているのか?
Q2 木琴の音階はどうなっていたのか?
Q3 どうして木琴に横棒は必要だったのだろう?
Q4 4人は一体どんな音楽を演奏したのだろう?
Q5 背景の違う4人が一緒に集まってセッションする状況はあり得たか?
5 5つの謎を実験する
3回のトークセッションを経て浮上した5つの謎をもとに、2つのワークショップを開催した。まず、美術家の荒野真司さんをゲストに招いて、Q1~Q3の謎に迫るワークショップを行った。
Q1の湾曲した桴であるが、大発見があった。荒野さん考案の桴は、持ち手の部分は竹で作り、先に木の球を取りつけるというものだった。岡田屋布施にあったのは、持ち手も木製だった。木製の桴は、湾曲部分にしなりがなかったが、竹製の桴は、非常にしなり弾力性の高いのが特長だ。実際に製作して木琴を叩いてみて驚いた。しなやかに湾曲した竹の弾力性で、初心者でも桴捌きが自然にできるのだ。真っ直ぐの桴と叩き比べてみると、違いは顕著だった。曲がった桴では弾んだ演奏ができる子どもが、真っ直ぐの桴では、鍵盤に押し付けるような演奏になってしまう。着物の裾が邪魔にならないよう、少ない動きで演奏できるように考案された桴ではないか、という意見も出た。江戸時代に竹製の湾曲した桴が実在したかどうかは不確かだが、この荒野式の桴は、非常に優れていると思う。
続いてQ2だが、浮世絵に現れる木琴の多くは、鍵盤の長さは同じで、厚薄のみでピッチの違いを作っているらしいので、そのやり方を踏襲して木琴を製作した。実際に削ってみると、削っても削っても微妙にしかピッチが下がらず悪戦苦闘した。しかし、逆に言うと、かなり微妙なピッチまで実現できるということでもある。厳密な音階を目指さないならば、わざわざ裏を削ってまで音の高さを変える必要があるだろうか? 何らかの音階に合わせて調律されていたはずだと確信したが、それがどんな音階かは、謎のままである。
Q3の横棒の製作だが、Q2の音階作りが想定以上に長時間を要したため、ワークショップで取り組むことはできなかった。これについては、後日、荒野さんと野村で試作することになるが、実際に横棒を作ってみて次のような説が浮上した。視覚障害者にとって、鍵盤から飛び出して演奏しないために、鍵盤の端を示すガイドとして使われていたのではないか、と。実際に、眼を閉じて横棒付の木琴を演奏してみると、確かに横棒がガイドになって、鍵盤の中央あたりの位置を叩き続けることができる。また、鍵盤を叩いた時に、鍵盤が微妙に浮き上がり横棒に接触する。その音を、三味線のさわりのような効果として活用しようとしたのではないか、というのが、もう一つの説。
Q4とQ5に答えるべく、4人の奏者を集めてのワークショップでは、4人はどんな状況でどんな音楽をしたのかを参加者に提案してもらい、それをその場で次々に実演してみるというものだった。実際に空想を音にしてみると、この四重奏という音色の組み合わせは、多様な表情を見せる。ワークショップでは、Q4に対して、
(1) 「巣ごもり地」という江戸時代にもあったオスティナートにのせて
(2) 木琴の音階に合わせたユニゾンの曲
(3) 木琴と箏でリズムユニゾン、胡弓が鳥、尺八が風のつもりで
(4) おどろおどろ系
(5) 木琴の合図で音を出すが、基本的には木琴の独奏。コンチェルト風
などを実験した。また、この4人が演奏する状況を空想してみると、ますます想像が膨らむ。Q5に対しては、
(1) 木琴と箏はプロで真面目に演奏している。そこに、現れた不真面目な虚無僧が加わり不穏な雰囲気に。通りかかった町民がきて笑いながら胡弓をやると、みんながおかしくなる
(2) 尺八が瞑想していて、木琴と胡弓が自由奔放にやると、箏はどうしていいか悩む
(3) 胡弓と尺八が遊び人で民謡を歌っている。箏と木琴は伴奏に雇われている
(4) 三味線を入れずにマイナー楽器でバンドやろうと集まった。
という案が出て、その状況を意識して演奏すると、それぞれが全く違った曲調になる。
それにしても、北斎漫画の四重奏を見て、よくもこれだけ多くの空想が浮かんでくるものだ、と思う。そういう謎を残す魅力が、この絵にはある。3回のトークと2回のワークショップを経た今、あの四重奏は、北斎が偶然一つの紙面上に書いただけで、実在しなかった、と感じている。あれは、きっと北斎の頭の中だけに存在していた音楽なのだと。そして、ぼく自身は、これから北斎漫画の四重奏の作曲に取り組むのだが、北斎の頭の中の音楽をどう再現するのか、しないのか? それは、江戸の人がインドネシアの木琴を真似ながら、江戸独特のものを作ってしまったように、北斎や江戸の音楽を再現しようとしているうちに、野村誠独特の音楽を書くことになるだろう。
(次回へ続く)
2010.2.13 update
